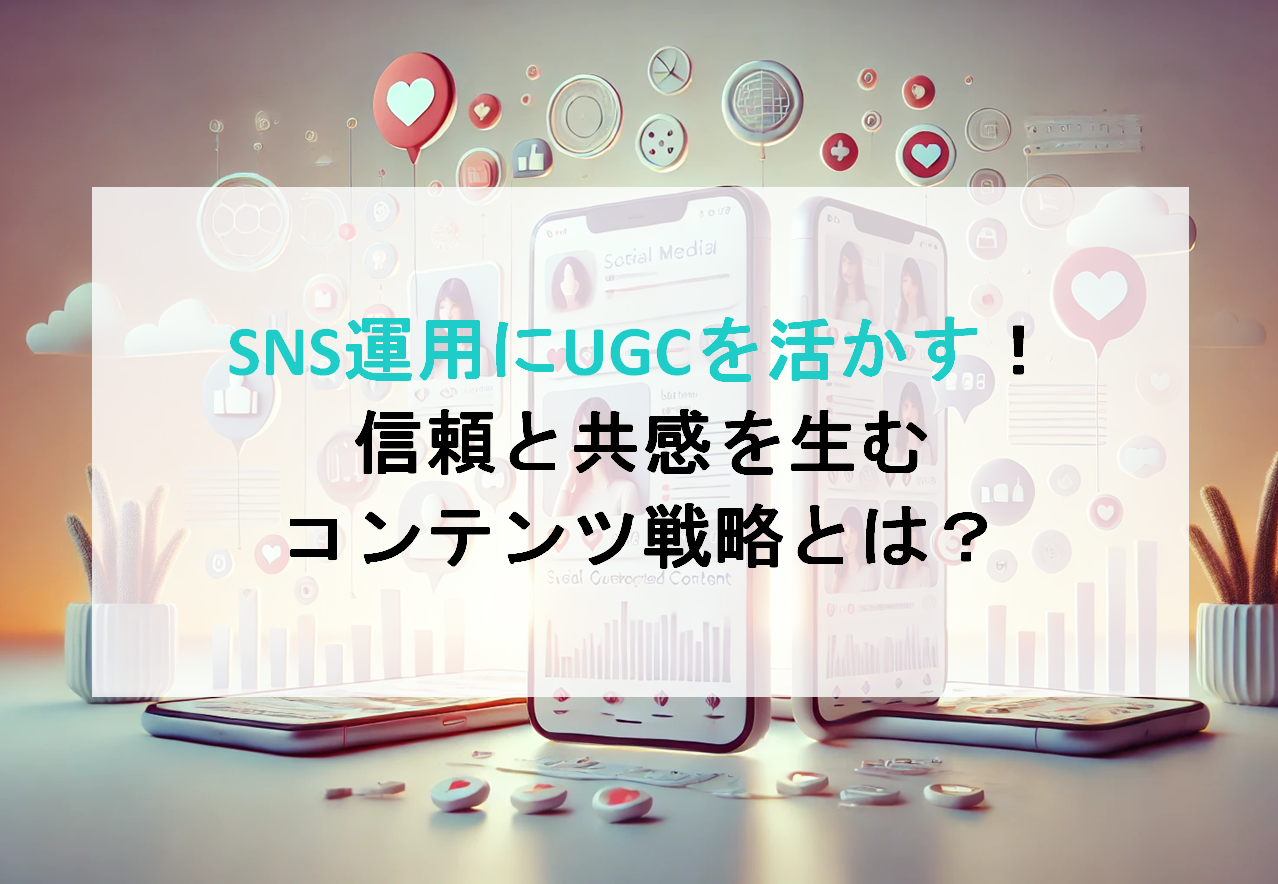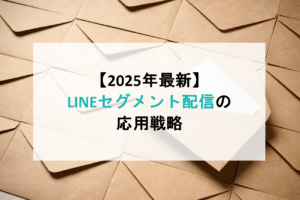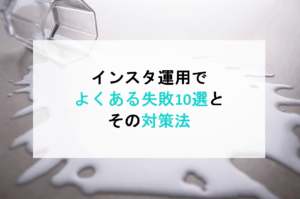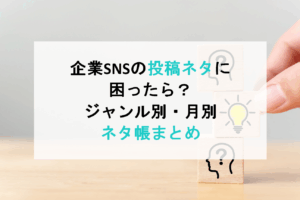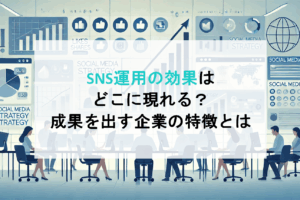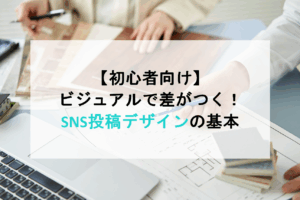SNSでの発信が企業の信頼性やブランドイメージに直結する現代において、企業が自社で制作するコンテンツだけでは情報発信に限界があります。
そこで注目されているのが、ユーザー自身が投稿する「UGC(ユーザー生成コンテンツ)」の活用です。
この記事では、UGCを効果的にSNS戦略に取り入れるためのメリットと具体的な実践方法について、運用担当者の目線でわかりやすく解説します。
UGCとは?企業SNSにおけるその価値
UGCとは「User Generated Content(ユーザー生成コンテンツ)」の略称で、一般ユーザーが自発的に作成・投稿するコンテンツを指します。
SNSでよく見られるのは、商品やサービスの利用体験に関するレビューや写真、動画などで、特にInstagram、X(旧Twitter)、TikTokといったプラットフォームで活発に活用されています。
企業にとってUGCの最大の価値は、「第三者による発信による高い信頼性」という点にあります。
例えば、企業が「この商品は素晴らしいです」と訴求するよりも、実際のユーザーが「実際に使ってみて良かった」と紹介する投稿の方が、情報を受け取る側にとって信頼感や共感を抱きやすいのです。
さらに、UGCはユーザーの率直な意見が集まるため、市場のリアルな反応を把握する手がかりとなります。
エンゲージメントの高いコンテンツが生まれやすく、ブランドへの親近感を育みやすいという点においても、企業のSNS運用において重要な資産と言えるでしょう。
UGCを活かしたSNS運用のメリットとは
UGCをSNS運用に取り入れることで、企業は大きな強化ポイントを得られます。
まず一つ目のメリットは、「広告のような印象を与えない自然なアプローチが可能になる」点です。
企業からの画一的なメッセージとは異なり、実際のユーザー体験に基づいたUGCは、フォロワーに押し付けがましさを感じさせることなく、受け入れられやすいという特徴があります。
また、UGCの存在は投稿コンテンツの多様性を高めるという点でも大きな利点となります。
例えば、自社の商品を利用したユーザーの投稿を紹介するだけでも、立派なコンテンツとなり、企業は無理なく発信頻度を維持できます。
さらに、UGCを活用することで、フォロワーとの双方向なコミュニケーションを促進できます。
「お客様の素敵な投稿をぜひ紹介させてください」といった形でユーザーを巻き込むことで、ブランドへの愛着が深まり、より強固な関係性を構築することが可能です。
コスト面においても、UGCは有利に働きます。
自社で写真や動画の撮影・制作を行う必要がなくとも、質の高い素材をユーザーが提供してくれることが多いため、プロモーションコストの削減にも繋がります。
UGCを集める仕組みとルールづくり
UGCは自然に生まれるものですが、企業が意識的に「集めやすい環境」を整備することで、その量と質を大幅に向上させることができます。
効果的なUGC収集と活用のためには、仕組みづくりとルール整備の両方が重要です。
・効果的なUGC収集の第一歩:ハッシュタグ戦略
まず最初に検討すべきは「ハッシュタグの設計」です。
ブランド独自ハッシュタグの作成: ブランド名やキャンペーン名を含むオリジナルのハッシュタグを用意することで、関連投稿の収集と検索が容易になります。
ユーザーのモチベーション向上: 投稿したユーザーにとっても「自分がブランドの一部として紹介されるかもしれない」という喜びが生まれ、積極的なUGC投稿を促します。
・参加型キャンペーンによるUGCの自然な創出
次に有効なのは、参加型のキャンペーン施策です。
インセンティブ設計: 「商品の使用写真に指定のハッシュタグを付けて投稿した方の中から抽選でプレゼント」といった企画は、UGCを自然な形で集めるための非常に効果的な仕組みです。
ターゲット層へのアプローチ: 特にSNSを日常的に利用している若い世代にとって参加のハードルは低く、口コミによる情報の拡散も期待できます。
・UGC活用におけるリスク管理:ルール策定の重要性
ただし、UGCを活用する際には「ルール策定」も不可欠です。
二次利用に関する許諾: 例えば、投稿コンテンツを企業のSNSやWebサイトなどで二次利用する際の許諾取得プロセスを明確化します。
権利関係への配慮: 著作権・肖像権に配慮したガイドラインを整備しておくことが重要です。
トラブル防止のための事前告知: 事前に利用条件を明確にした上で、投稿者から承諾を得ることで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
安心かつ効果的にUGCを活用するためにも、収集の仕組みと利用ルールはセットで考えることが重要です。
UGCの活用事例と成果を最大化するポイント
UGCを効果的に活用している企業事例として、例えばオルビス株式会社のX(旧Twitter)投稿が挙げられます。
同社は「企業6000ありがとうキャンペーン」と題し、フォロー&リポストによる応募に加え、「お祝いコメントもほしいナ!」と親しみやすい表現でユーザーの投稿(リプライ)を促しています。
このような言葉がけによって、単なるプレゼント企画に留まらず、ブランドへの祝福や好意的な意見といったUGCが集まりやすくなり、ポジティブな感情が広がる仕組みが構築されています。
?緊急企画?
◣フォロー&リポストで応募◢#オルビス企業6000ありがとう キャンペーン!
【6名様】に「エッセンスイン ヘアミルク」をプレゼント?◆応募方法◆
①@ORBIS__Inc をフォロー
②この投稿をリポスト良ければリプライでお祝いコメントをください? pic.twitter.com/WAwQqoQo32
— オルビス株式会社 (@ORBIS__Inc) February 7, 2025
また、ブルボンのInstagramでは、「どのお菓子を選ぶ?」という選択式の投稿が定番となっており、ユーザーに気軽なコメント参加を促しています。
このように「どれが好き?」「番号で答えてね」といった問いかけは、参加への心理的なハードルが低く、コメントという形のUGCを自然に生み出す上で非常に効果的です。
商品の魅力的なビジュアルも相まって、ブランドとユーザーの間に温かい交流が生まれるきっかけとなっています。
この投稿をInstagramで見る
これらのUGCは、通常のフィード投稿に加えて、ストーリーズやハイライト、リール動画など、SNSの多様な機能を横断的に活用することで、さらなる拡散効果が期待できます。
特にコメントやリプライは、SNSのアルゴリズム評価にも影響するため、UGCが集まるような設計は、投稿全体のリーチ拡大にも繋がります。
さらにUGCを紹介する際には、企業側から一言「〇〇さんの投稿、とても素敵でした!」といったコメントを加えることで、ユーザーへの敬意が伝わり、投稿した側の満足度も向上します。
「共にブランドを創り上げている」という感覚を共有してもらうことが、UGC活用の最大の価値と言えるでしょう。
まとめ
UGCは、SNS運用においてユーザーとブランドの距離を縮め、信頼と共感を育む強力な要素です。
自社からの発信だけでは届きにくい、生の声をコンテンツとして活用できる点が最大の魅力と言えるでしょう。
UGCには広告のような押し付けがましさがなく、自然な説得力があり、投稿頻度やコミュニケーションの質を高める上でも有効です。
そのためには、UGCが集まりやすい仕組みと明確なルールを整備することが不可欠です。
オルビスやブルボンの事例のように、コメントや選択肢を巧みに活用することで、ユーザーは楽しみながらUGCの作成に参加できます。
UGCを単なる「素材」として捉えるのではなく、「共創の証」として尊重する姿勢こそが、今後のSNS運用をより強固なものにしていくはずです。
SNS運用代行|インスタ運用代行は
クロス・プロップワークスへ
⏬️画像をクリックすると、サービス詳細ページへ移動します⏬️
クロス・プロップワークスでは、SNS運用代行サービスを提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
?気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください。
[jin-button-flat visual=”” hover=”down” radius=”50px” color=”#44d1df” url=”https://kwlg-box.jp/contact/” target=”_self”]サービスに関するお問い合わせはこちら>[/jin-button-flat]