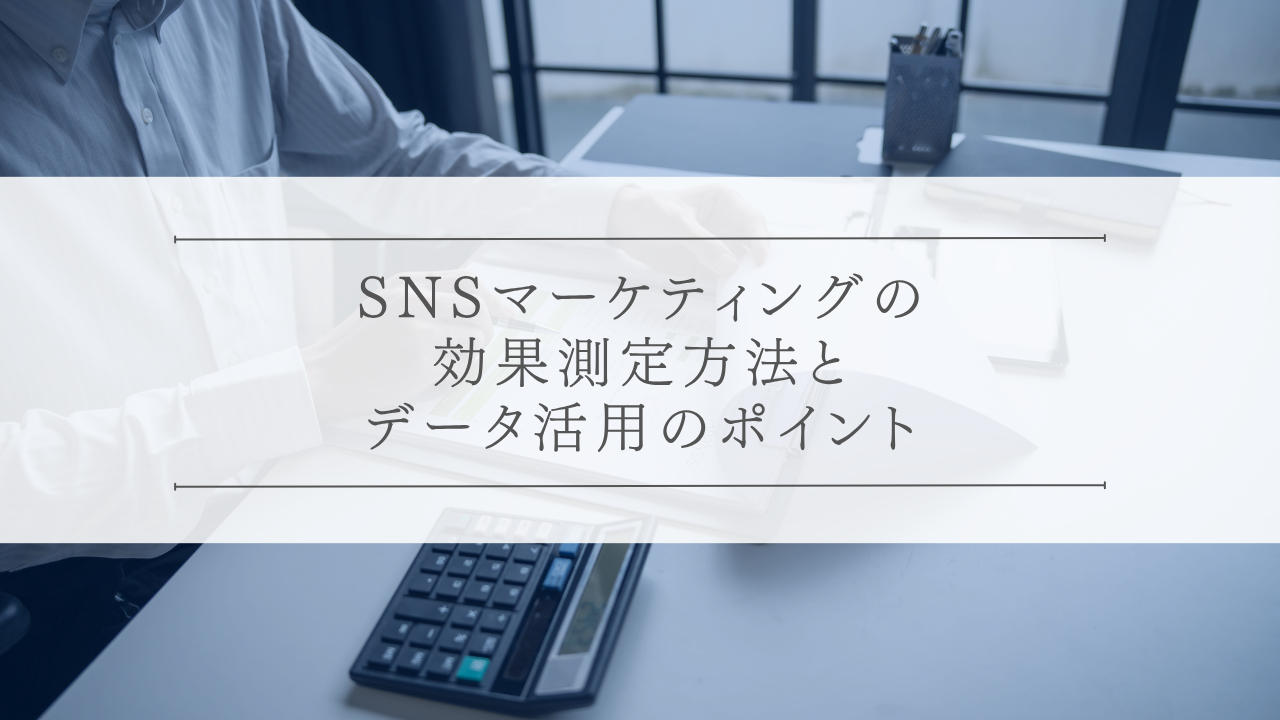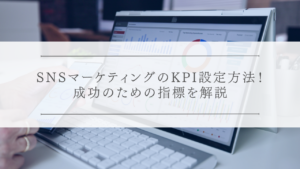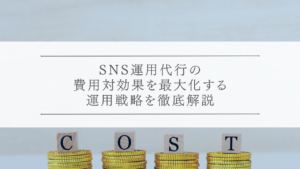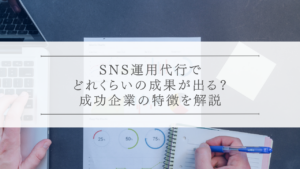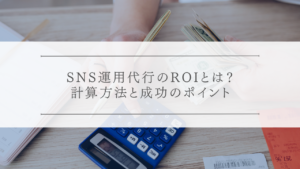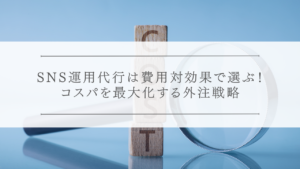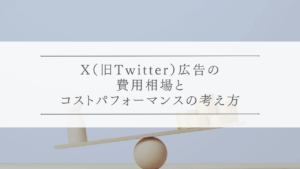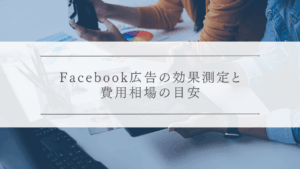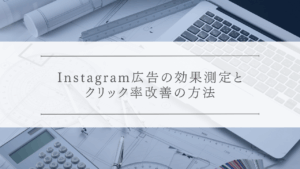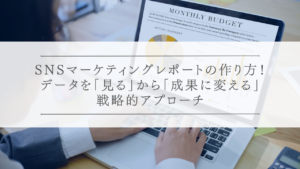SNSマーケティングは、施策の結果を正しく測定し、そこから得たデータを次のアクションに活かすことで初めて意味のある運用となります。ですが、実際には「どの数字を見ればいいのかわからない」「データをどう改善に繋げればいいのか悩んでいる」というご担当者様も多いのではないでしょうか。本記事では、SNSマーケティングにおける効果測定の方法と、その後のデータ活用のポイントについて、現場の実例を交えながらわかりやすく解説していきます。
SNSマーケティングで押さえるべき主要KPIとは?
SNSマーケティングにおける効果測定の出発点は、KPI(KeyPerformanceIndicator:重要業績評価指標)を正しく設定することです。しかし、どの指標を重視すべきかは、目的やプラットフォームの特性によって大きく異なります。
基本的な指標とその「落とし穴」
まず、SNS運用において最も基本的でわかりやすい指標として、フォロワー数、インプレッション数(投稿が表示された回数)、そしていいね数が挙げられます。これらはアカウントの規模やコンテンツがどれだけ広がったかを知るための土台となる数字です。
しかし、多くのご担当者様が陥りがちなのが、この「見た目の数字」だけを追いかけてしまうという落とし穴です。例えば、フォロワー数が多くても、それが自社のサービスに全く関心のない層であれば、ビジネスの成果には繋がりません。これらは「虚栄の指標(VanityMetrics)」とも呼ばれ、レポート上は見栄えが良いものの、実際の事業貢献度とは乖離がある場合も少なくないのです。私たちがご支援する中でも、「とにかくフォロワーを増やしたい」というご要望は多いですが、その先に何を目指すのかを明確にすることが、成果を出すための第一歩となります。
事業成果に繋がる「一歩進んだKPI」
基本的な指標の先にある、より事業成果と結びつきの強い「意図の指標(IntentMetrics)」に目を向けることが重要です。これは、ユーザーがどれだけ強い興味や関心を示したかを表す数字です。
Instagramの例:あるイベントの告知投稿で、リーチしたアカウント数が189,724件だったとします。この数字も重要ですが、私たちがさらに注目するのはプロフィールアクセス率です。この事例では、実に25.13%ものユーザーが投稿を見た後にプロフィール画面を訪れていました。これは、単に投稿を眺めるだけでなく、「このアカウントは誰だろう?」と能動的に興味を持ったユーザーが4人に1人もいたことを示しており、いいね数よりもはるかに質の高い関心の現れと言えます。
目的とプラットフォーム特性でKPIを使い分ける
KPIは、すべてのSNSで同じものを設定すれば良いわけではありません。例えば、弊社の調査によると、以下のグラフが示すように、ユーザーはプラットフォームごとに異なる使い方をしていることがわかっています。10代・20代の若年層は、GoogleだけでなくInstagramやX(旧Twitter)を検索エンジンとして積極的に利用しています。
この事実から、若年層をターゲットとするブランドがInstagramを運用する場合、発見タブからの流入数やハッシュタグ検索経由のリーチ数は非常に重要なKPIとなります。一方で、LINEのようなクローズドなコミュニケーションツールでは、既存顧客との関係性を深めるためのクーポン利用率やブロック率の推移などが、より目的に合ったKPIと言えるでしょう。
成果を可視化するための分析ツールと活用法
各SNSプラットフォームには、標準で分析ツール(Instagramインサイト、Xアナリティクスなど)が備わっており、これらが効果測定の基本となります。しかし、ツールが提示する数字を眺めるだけでは不十分です。大切なのは、その数字の背景を読み解き、次の一手となる仮説を立てることです。
現場の事例から学ぶデータの読み解き方
例えば、過去2年間の投稿の中で、ある「デジタルクーポンブック」の投稿が最も多い「保存数」を記録した事例があります。私たちは、この「保存」というアクションを、いいねのような瞬間的な好意を示すもの以上に重要視しています。保存は「後で見返したい」という強い関心の現れであり、ユーザーにとって価値の高い情報であったことを示唆しているからです。さらに、この投稿のホーム率(フォロワーのホーム画面から表示された割合)も31.14%と高い水準でした。このデータから、「フォロワーに対して非常に有益な情報を提供できた結果、高い関心を引き出し、保存という行動に繋がった」という仮説を立てることができます。この分析から、「次回も同様のクーポンや特典情報を発信することで、フォロワーのエンゲージメントを高められるのではないか」という具体的な改善アクションに繋げることができるのです。これこそが、データを「活かす」ということです。
データに基づいた改善アクションの考え方
効果測定は、改善アクションとセットであって初めて意味を持ちます。「観測→分析→実行」のサイクルを回し続けることが、SNSアカウントを成長させる唯一の方法と言っても過言ではありません。ここでは、現場でよく見られるデータと、それに対する改善アプローチの考え方を具体的にご紹介します。
| 観測データ | 考えられる原因 | 改善アクションの具体例 |
|---|---|---|
| LINEのメッセージクリック率が低い | 配信コンテンツとターゲットの興味が合っていない。クリエイティブ(画像)がユーザーの目に留まっていない。 | 配信先をセグメントし、年代や興味関心に合わせた内容に最適化する。リッチメッセージとカードタイプなど、異なる画像フォーマットでA/Bテストを実施し、反応率を比較検証する。 |
| Instagramのプロフィールアクセス率は高いが、フォローに繋がっていない | プロフィール自体に魅力がない。アカウントの世界観が不明確で、フォローするメリットが伝わっていない。 | プロフィール文を最適化し、ユーザーに提供できる価値(例:「役立つ情報」「お得な情報」など)を明確に記述する。アカウントの世界観を象徴する投稿を3件プロフィール上部に固定表示し、アカウント全体のトンマナを統一する。 |
| キャンペーン投稿の反応は良いが、通常投稿のエンゲージメントが低い | ユーザーはキャンペーンの景品にのみ興味があり、アカウント自体のファンではない。普段のコンテンツがユーザーの知りたい情報とズレている。 | エンゲージメントが高かった投稿を分析し、成功要因(例:有益性、共感性、デザイン)を抽出して通常投稿に活かす。ストーリーズのアンケート機能などを活用し、フォロワーがどのような情報を求めているか直接ヒアリングする。 |
このような地道な仮説検証を繰り返すことが、戦略的なSNS運用代行サービスの核となります。
数字で終わらせない、SNS運用を“育てる”データ活用術
SNSは短期的な数字だけでなく、長期的な視点でブランドの資産を築くためのツールです。そのためには、目先の数字に一喜一憂せず、データを活用してアカウントを「育てる」という視点が不可欠になります。
「バズ」より「ファン」。短期的な指標の危うさ
SNS運用において、「バズらせたい」というご要望をいただくことは少なくありません。確かに、一時的に大きな注目を集める「バズ」は認知度向上に貢献することもあります。しかし、私たちはその危うさについてもクライアントにお伝えしています。
バズを狙うあまり過激な表現や奇をてらった企画に走ると、意図せず炎上につながるリスクがあります。また、仮にバズが成功したとしても、集まってきたユーザーが自社のターゲット層と異なっていれば、それは一過性のお祭りで終わり、長期的なビジネス成果には結びつきません。私たちがSNS運用代行サービスを通じて本当に目指しているのは、短期的な話題性よりも、「じわじわとブランドへの信頼を育て、長期的なファンを増やすこと」です。質の高い情報を継続的に発信し、誠実なコミュニケーションを重ねることで築かれたファンとの関係こそが、企業の揺るぎない資産となります。
成功の鍵は「データ分析と改善サイクル」にある
では、どうすればSNS運用を成功に導けるのでしょうか。その答えは、データの中にあります。下記のグラフは、SNS運用が上手くいっていると回答した企業に、その成功要因を尋ねた弊社の調査結果です。最も多く挙げられたのは、「データ分析による改善サイクルが実行できている」ことでした。
さらに興味深いのは、同じ調査で、自社のみで運用している企業よりも、外部のSNS運用代行サービスを活用している企業の方が「運用がうまくいっている」と回答した割合が顕著に高かったという事実です。これは、専門家が体系的なプロセスに則ってPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を回し続けることが、いかに重要であるかを示唆しています。SNS運用の成功は、魔法のような裏技によってもたらされるのではなく、データに基づいた地道な改善活動の積み重ねによって実現されるのです。
組織でデータを活用し、アカウントを資産に変える
SNSから得られるデータは、SNS運用の改善だけに留まらない、非常に大きな価値を秘めています。それは、顧客を理解し、事業全体を改善するための「ビジネスインテリジェンス」としての価値です。
例えば、ある商業施設のLINE公式アカウントで実施したアンケートでは、「施設を何で知りましたか?」という質問に対し、「知人紹介」「通りがかり」に次いで「Instagram」が3番目に多い結果となりました。このデータは、SNS担当者だけのものではありません。
- 営業・店舗担当者へ:「知人紹介」が多いという事実は、口コミの重要性を裏付けており、顧客満足度を高める施策や紹介キャンペーンの有効性を示唆します。
- 経営層へ:「Instagram」が主要な認知経路の一つであるというデータは、SNSへの投資対効果を具体的に示し、今後のマーケティング予算の適切な配分を判断する材料となります。
このように、SNSデータを組織全体で共有し、多角的に活用することで、SNSアカウントは単なる情報発信ツールから、事業成長に貢献する戦略的な「資産」へと進化するのです。
まとめ:成功の鍵は、「数字の先」にあるインサイト発見
SNSマーケティングは、投稿の数やフォロワー数をただ追いかけるだけでは、その効果を最大化することはできません。自社の目的に合ったKPIを正しく設定し、ツールを使って得られたデータを分析し、そして具体的な改善アクションを繰り返す。この一連のサイクルを回し続けることで、初めて戦略的で成果の出る運用が可能になります。
大切なのは、数字の表面だけを見て一喜一憂するのではなく、その裏側にあるユーザーの「意図」や「インサイト」を読み解こうとすることです。ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、数字に振り回されるのではなく「データを活かしたアカウント育成」を目指してみてください。専門的な知見やリソースが必要な場合は、SNS運用代行サービスのような外部パートナーと連携することも、有効な選択肢の一つとなるでしょう。
SNS運用代行ならクロス・プロップワークス
クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!