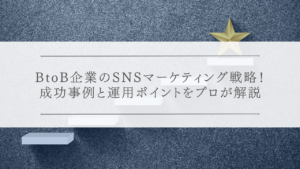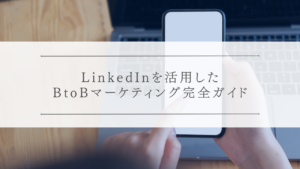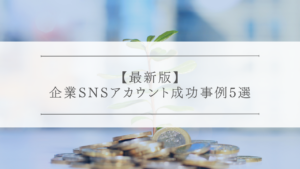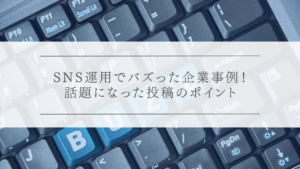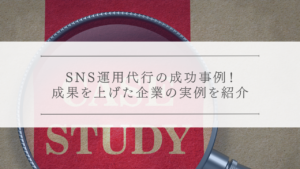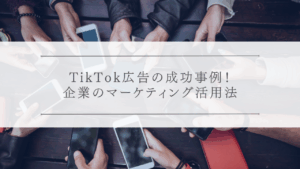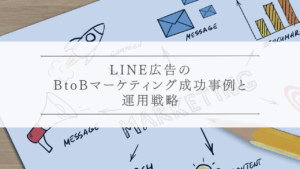BtoB事業を展開する企業のご担当者様から、「SNSの重要性は理解しているけれど、何から手をつければ良いかわからない」「自社の商材は専門的すぎて、SNSには向かないのでは?」といったお悩みをよくお聞きします。SNSはBtoC向けのもの、というイメージがまだ根強いかもしれません。
しかし、BtoB企業にこそ、SNSは長期的な信頼関係を築き、ブランド価値を高めるための強力な武器となり得ます。大切なのは、単に流行を追うのではなく、自社の目的と強みに合った「考え方」で運用することです。
この記事では、実際にSNS運用で大きな成果を上げているBtoB企業5社の事例を深く掘り下げます。単なる成功パターンの紹介ではなく、
その裏側にある戦略的な「考え方」に焦点を当てて解説します。この記事を読み終える頃には、自社がSNSとどう向き合うべきか、そして専門的なSNS運用代行サービスを活用する価値はどこにあるのか、明確なヒントが得られるはずです。
なぜ今、BtoB企業にこそSNS運用が重要なのか?
成功事例を見る前に、まず「なぜBtoB企業にとってSNSが重要なのか」という根本的な問いについて、少しだけ考えてみたいと思います。その理由は、顧客の購買行動の変化にあります。
かつてのBtoBの購買プロセスは、営業担当者からの情報提供が中心でした。しかし現在、企業の意思決定者たちは、営業担当者に接触するずっと前の段階で、インターネットやSNSを駆使して広範な情報収集を行っています。実際に、私たちの調査でも、調べ物をする際にGoogle検索に次いでX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeといったSNSが利用されている実態が明らかになっています。これは、BtoBの顧客もまた、一人の生活者として日常的にSNSで情報に触れていることを意味します。
ここで一つ、私たちが現場でよく目にする誤解を解いておきたいと思います。それは、「SNSは短期的な売上を作るためのツールだ」という考え方です。BtoBにおけるSNSの真の価値は、目先の取引ではなく、長期的な信頼の蓄積にあります。高額で、導入の意思決定が複雑なBtoB商材の場合、一つの投稿がきっかけで即座に契約に至ることは稀です。むしろ、継続的に専門性の高い情報を発信し、企業の姿勢や価値観を伝えることで、「この分野なら、あの会社が信頼できる」という認識を時間をかけて醸成していくことが何よりも重要なのです。
このような戦略的な情報発信には、専門知識と継続的なリソースが不可欠です。だからこそ、多くの企業が「専門知識がない」「リソースが不足している」といった理由で、プロフェッショナルなSNS運用代行サービスの活用を選択肢に入れています。
成果を出すBtoB企業のSNS運用成功事例5選
それでは、具体的にどのような企業が、どのような考え方でBtoBのSNS運用を成功させているのでしょうか。ここでは、多様な業種の5つの事例を、その核心となる戦略と共に見ていきましょう。
①株式会社AGC:複数媒体を使い分ける「メディアポートフォリオ戦略」
素材メーカーとして世界的に知られる株式会社AGCは、複数のSNSを巧みに使い分けることで、多様なステークホルダーとのコミュニケーションを実現しています。この戦略の鍵は、各SNSの特性とターゲット層を深く理解し、それぞれに最適化された役割を与える「ポートフォリオ」の考え方にあります。
例えば、同社のYouTubeチャンネルでは、企業の全体像を紹介する動画や、化学品事業の根幹である「ケミカルチェーン」を詳細に解説する映像、さらには決算説明会といった、専門的で深い情報が発信されています。これは明らかに、技術者や投資家、ビジネスパートナーといった、同社の事業に深い関心を持つ層に向けたコンテンツです。
一方で、X(旧Twitter)では「AGCちゃん」というオリジナルキャラクターを立て、親しみやすいトーンでユーザーとの交流を図っています。ここでは専門的な話は控えめに、ブランドへの親近感を醸成することが主目的です。さらにTikTokでは、若年層をターゲットに「#AGCチャレンジ」というキャッチーな企画で、まずは社名を知ってもらうという、広い認知獲得に特化しています。
多くの企業が陥りがちなのが、「どのSNSでも同じ情報を発信してしまう」という過ちです。しかしAGC社の事例は、「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という目的をプラットフォームごとに明確に定義することの重要性を示しています。このような戦略的な役割分担は、各チャネルへの投資対効果を最大化させます。これは、高度な専門知識を要するSNS運用代行サービスが最も価値を発揮できる領域の一つと言えるでしょう。
②サイボウズ株式会社:企業理念を体現する「世界観ブランディング」
グループウェアで有名なサイボウズ株式会社のSNS運用は、単なる製品プロモーションに留まりません。彼らの発信の根底には、「チームワークあふれる社会を創る」という一貫した企業理念があります。
同社のX(旧Twitter)アカウントを覗くと、製品の機能紹介だけでなく、同社独自の企業文化(例えば、社内版Twitterとも言える「分報」の取り組み)や、能登半島地震への支援活動といった社会貢献、さらにはインフレ特別手当の支給といった先進的な人事施策まで、実に多様な情報が共有されています。
これは、製品の「機能(What)」を売るのではなく、その背景にある「思想(Why)」を伝え、共感を呼ぶという高度なブランディング戦略です。BtoB、特にSaaS(SoftwareasaService)のような継続的な関係性が求められるビジネスにおいて、顧客は単なるツールではなく、事業を共に推進するパートナーを選んでいます。サイボウズはSNSを通じて、「私たちはこんな価値観を大切にする会社です」というメッセージを発信し続けることで、その価値観に共鳴する人々を惹きつけているのです。
このような運用は、短期的な成果を追い求めるのではなく、時間をかけてブランドへの信頼と愛着を育てる「ファンづくり」に他なりません。これは、企業としてのあり方そのものが問われるため、表面的なテクニックだけでは決して真似のできない、本質的なSNS活用の好例です。
③株式会社石井精工:専門知識を解放する「ニッチトップ戦略」
「うちのような町工場の仕事は、地味で専門的すぎてSNSには向かない」そう考える中小製造業の方は少なくないかもしれません。しかし、ゴム成形用金型の設計・製造を手がける株式会社石井精工は、その常識を覆しました。
同社のYouTubeチャンネル「石井精工のゴム金型ch」で人気を集めているのは、きらびやかなプロモーション動画ではありません。「ゴム製品はこう作られている!」(再生回数2万回超)や、「タップ加工のトラブル解決」(同4.3万回超)といった、現場の専門知識やノウハウを惜しみなく公開する、極めて専門的なコンテンツです。
この戦略が成功している理由は、ターゲットを明確に絞り、彼らが本当に求めている「価値」を提供しているからです。同社の動画を見ているのは、同業者である技術者や、製品開発に課題を抱える企業の担当者、そしてものづくりに興味を持つ未来の働き手たちです。彼らはエンターテインメントではなく、課題解決のための「知識」を求めています。
石井精工は、自社の持つ専門知識という「無形の資産」を解放することで、業界内での圧倒的な信頼と権威性を築き上げました。さらに、同社のYouTubeチャンネルは、採用活動においても大きな役割を果たしていると公言しています。これは、マーケティングと採用を同時に実現する、非常に効率的で強力な戦略です。どんなニッチな業界であっても、その中に眠る専門知識は、SNSを通じて価値あるコンテンツになり得ることを証明しています。
④GMOサイン:親しみやすさで壁を壊す「キャラクター活用術」
電子契約サービスという、形がなく、やや専門的で硬い印象を与えがちなBtoBサービスを、巧みなSNS運用で身近な存在に変えているのがGMOサインです。その鍵を握るのが、公式キャラクターの活用です。
電子契約のようなサービスは、その利便性を理解するまでに少しハードルがあります。そこでキャラクターが「ブランドの顔」として登場することで、サービスに人間味と親しみやすさが生まれます。ユーザーは企業に対してではなく、キャラクターに対して質問したり、反応したりすることで、コミュニケーションの心理的な壁がぐっと下がるのです。
また、キャラクターはリポストキャンペーンの案内役を務めたり、他の企業アカウントと交流したりと、アカウントの「中の人」として一貫したトーンでコミュニケーションを担います。これにより、無機質になりがちなBtoBの企業アカウントに、一貫した「人格」と「温かみ」を与えることに成功しています。
機能や価格での差別化が難しい競争の激しい市場において、こうした「ブランドの個性」や「親しみやすさ」は、顧客が最終的にどのサービスを選ぶかを左右する重要な要素になり得ます。専門的なサービスをいかに分かりやすく、親しみやすく見せるか。その一つの答えが、このキャラクター活用術にあると言えるでしょう。
⑤デロイトトーマツグループ:圧倒的情報量で見せる「信頼性の構築」
世界最大級のプロフェッショナルサービスファームであるデロイトトーマツグループは、その圧倒的な知見をSNS上で示すことで、揺るぎない信頼性を構築しています。彼らの戦略は、「圧倒的な情報発信量と質によって、ソートリーダーシップ(特定の分野における第一人者としての地位)を確立する」というものです。
同社のX(旧Twitter)アカウントは、ほぼ毎日更新され、その内容はイベントの告知、最新の調査レポートのリリース、採用情報、そして新たなコンサルティングサービスの発表など、極めて多岐にわたります。
この一連の発信は、単なるお知らせではありません。これは、「私たちは常にビジネスの最前線で、これだけ広範かつ専門的な知見を生み出し続けている企業です」という、強力なメッセージになっています。彼らにとって、SNSで発信する一つひとつの情報が、自社の知的レベルを証明するポートフォリオなのです。
このような戦略を実行するためには、社内の様々な部署から情報を集め、SNSに適した形に編集し、継続的に発信し続けるという、高度に組織化されたコンテンツ制作体制が不可欠です。これは、多くの企業にとって大きな負担となりますが、だからこそ、戦略立案からコンテンツ制作、投稿管理までを一貫して担うSNS運用代行サービスの専門性が活きる領域でもあります。
成功事例から学ぶ、BtoBのSNS運用で失敗しないための3つの鉄則
ここまで5つの成功事例を見てきました。これらから、業界や企業規模を問わず通用する、BtoBのSNS運用における普遍的な成功法則を3つ、導き出すことができます。
①「目的」と「役割」を明確にする
成功している企業はすべて、SNS運用における「目的」が明確です。AGC社がプラットフォームごとに役割を分けていたように、「このSNSを通じて、誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」を定義することが出発点となります。
「とりあえずSNSを始めよう」という漠然とした動機では、投稿内容がブレてしまい、成果には繋がりません。私たちの調査でも、SNS運用がうまくいっている企業は「明確な戦略設計と目標設定ができている」と回答する割合が高いことがわかっています。自社の目的が「ブランドの認知拡大」なのか、「専門家としての信頼獲得」なのか、あるいは「採用強化」なのか。まずその目的を定めることが、失敗しないための第一歩です。
②「売り込み」ではなく「信頼の蓄積」に徹する
サイボウズ社や石井精工社の事例が示すように、BtoBのSNS運用は、短期的な「売り込み」の場ではありません。むしろ、長期的な視点で、じわじわと「信頼を蓄積」していくための活動と捉えるべきです。
一時的に注目を集める「バズ」も無意味ではありませんが、BtoBにおいて本当に重要なのは、一過性のお祭り騒ぎではなく、日々の地道な情報発信を通じて「この会社は信頼できる」という評価を積み上げていくことです。成果がすぐに出ないからといって諦めてしまうのは、最も避けたい失敗です。SNSはマラソンのようなもの。焦らず、辛抱強く、価値ある情報を提供し続ける姿勢こそが、最終的に大きな成果となって返ってきます。
③「自社らしさ」を武器にする
今回ご紹介した5社は、決して他社の真似をしたわけではありません。AGCのグローバルな技術力、サイボウズの独特な企業文化、石井精工の職人的な専門性。それぞれが自社にしかない「らしさ」や「強み」を深く理解し、それをSNS運用の核に据えていました。
自社の「らしさ」は、中にいると意外と気づきにくいものです。商品やサービスに愛情があるあまり、顧客が本当に知りたい情報との間にズレが生じてしまうことも少なくありません。客観的な視点を持つ外部のパートナー、例えば経験豊富なSNS運用代行サービスは、自社では見過ごしがちな独自の強みを発見し、それを魅力的なコンテンツへと昇華させる手助けをしてくれます。私たちの支援プロセスでも、この「自社らしさの再発見」から戦略を組み立てることが非常に多くあります。
まとめ:BtoBのSNS運用は、信頼できるパートナー選びが成功の鍵
今回は、BtoB企業のSNS運用について、5つの成功事例とその裏にある「考え方」を掘り下げてきました。
これらの事例からわかるのは、BtoBにおけるSNS運用が、単に投稿作業をこなすだけの単純な業務ではないということです。それは、企業のブランド価値を構築し、顧客との長期的な信頼関係を育むための、極めて戦略的な活動です。プラットフォームの選定、目的の明確化、一貫した世界観の構築、そして価値あるコンテンツの継続的な提供。これらすべてを高いレベルで実行し続けるには、相応の専門知識とリソース、そして何よりも粘り強さが求められます。
自社だけで全てをまかなうのが難しいと感じた場合、専門家の力を借りることは非常に有効な選択肢です。私たちの調査では、SNS運用を外部に委託している企業の方が、「データ分析による改善サイクルが実行できている」と回答する割合が高く、結果として成果に繋がりやすい傾向が見られます。
優れたSNS運用代行サービスは、単なる作業代行者ではありません。企業の目的と課題を深く理解し、その「らしさ」を最大限に引き出しながら、共に汗をかく戦略的パートナーです。この記事が、貴社のSNS戦略を見つめ直し、ビジネスをさらに加速させるための一助となれば幸いです。
SNS運用代行ならクロス・プロップワークス
クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!