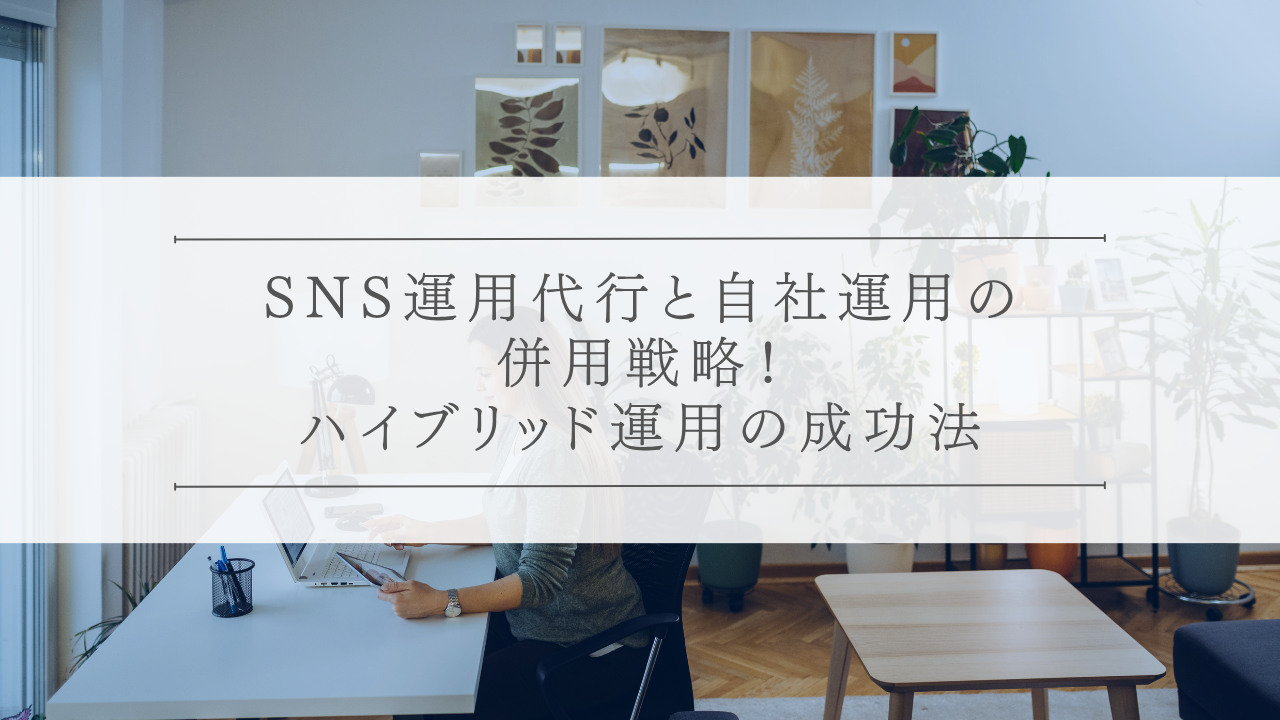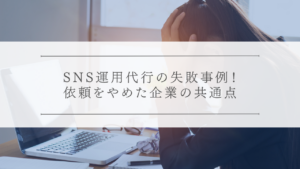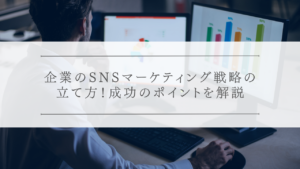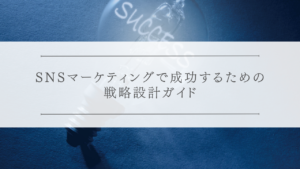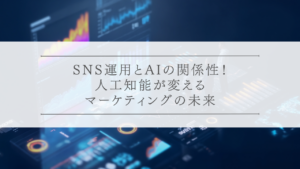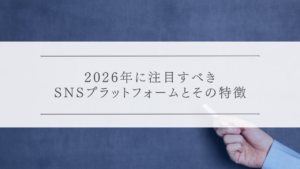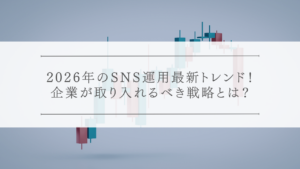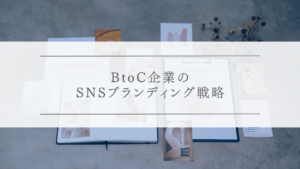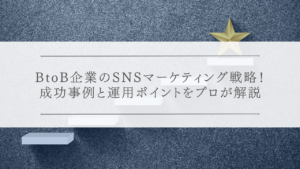企業のSNS活用が当たり前となった今、多くの担当者様が「どんな情報を発信すればいいのか」「どうすれば継続できるのか」といった運用の具体的な方針について課題を抱えています。社内のリソースを割いて自社で運用すべきか、それとも専門知識を持つプロ、つまりSNS運用代行サービスに全てを委託すべきか。この二つの選択肢の間で悩むこともあるでしょう。しかし、実は「自社運用」か「外部委託」かという二択だけが道ではありません。
本記事では、それぞれの強みを活かし、弱点を補い合う「ハイブリッド運用」という第三の選択肢に焦点を当て、その具体的な進め方と成功の秘訣を、SNS運用のプロの視点から解説します。
自社運用のメリット・デメリットを正しく理解する
SNS運用を自社で行うことには、確かに大きな魅力があります。何よりも、自社の商品やサービスに対する深い理解と熱い想いを、ダイレクトに情報発信に活かせる点は大きな強みです。新商品の情報や緊急性の高いアナウンスも、社内だからこそ迅速に発信できますし、日々の運用を通じて得られた知見やデータは、企業の貴重な資産として社内に蓄積されていきます。
しかし、その一方で、自社運用にはいくつかの壁が存在することも事実です。「SNS運用は、他の業務の片手間でもできるのでは?」というお声をいただくこともありますが、それは大きな誤解です。なぜなら、質の高いコンテンツを継続的に企画・制作し、ユーザーとコミュニケーションを取り、さらに効果測定と改善を繰り返すという本格的な運用には、相応の時間と労力、そして専門知識が不可欠だからです。
実際、多くの企業様から「専門知識を持つ人材がいない」「最新トレンドを追いかけるのが大変」といったお悩みを伺います。また、リソース不足から「毎日投稿することが目的になってしまい、内容が伴わない」といった「自社運用の罠」に陥ってしまうケースも少なくありません。愛情が深いあまり、つい企業目線の「伝えたいこと」が先行し、ユーザーが本当に「知りたいこと」との間にズレが生じてしまう、というのもよくある話です。
以下に、自社運用の主なメリットとデメリットをまとめました。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| ブランド理解度 | 非常に深い | 客観的視点が欠けやすい |
| スピード・柔軟性 | 社内情報への迅速な対応、意思決定の速さ | 担当者のスキルやリソースに依存 |
| コスト(運用) | 外部委託費は不要 | 人件費、担当者の教育・育成コスト、ツール導入費などがかかる可能性がある |
| 専門性・ノウハウ | 運用を通じて社内に蓄積される | 最新情報のキャッチアップや専門スキル習得が難しい |
| リソース | 状況に応じて調整可能 | 担当者の負担増、他業務との兼任によるリソース不足が起こりやすい |
| 客観性 | 顧客との直接対話から得られるインサイトがある | 自社製品・サービスへの思い入れが強く、客観的判断が難しい場合がある |
| 情報発信の一貫性 | 企業理念に基づいた一貫したメッセージをコントロールしやすい | 担当者変更によるトーンの変動リスク |
| 社内ノウハウ蓄積 | 成功・失敗体験が直接的な学びとなり、組織の資産として蓄積される | 属人化しやすく、担当者の異動・退職で失われるリスクがある |
これらの点を踏まえ、自社の状況と照らし合わせて冷静に判断することが、SNS運用成功の第一歩と言えるでしょう。
運用代行のプロを活用する利点とリスク
自社運用の課題を解決する選択肢として、「SNS運用代行サービス」の活用があります。ここで言うSNS運用代行サービスとは、単に投稿作業を代行するだけでなく、現状分析から戦略立案、コンテンツの企画・制作、日々の運用管理、効果測定、そして改善提案まで、SNS運用に関わる多岐にわたる業務を専門的にサポートするサービスを指します。
プロのSNS運用代行サービスを活用する最大の利点は、やはりその専門性と経験です。SNSのトレンドは目まぐるしく変化し、各プラットフォームのアルゴリズムも頻繁に更新されます。こうした変化に常にアンテナを張り、最新情報と豊富な事例に基づいて最適解を導き出せるのは、専門家ならではの強みと言えるでしょう。支援の現場では、「とにかくバズりたい」というご要望をいただくこともありますが、短期的な話題性よりも、「じわじわとブランドへの信頼を育て、長期的なファンを増やすこと」を重視しています。一過性のお祭りで終わらせず、継続的に企業価値を高めていく視点からのサポートは、大きなメリットです。
また、SNS運用にかかる多大なリソースを外部に委託することで、社内の担当者は本来のコア業務に集中できます。結果として、企業全体の生産性向上にも繋がり得るのです。
しかし、SNS運用代行サービスの利用には、もちろん注意すべき点やリスクも存在します。注意点として、まず費用対効果の見極めが挙げられます。適正価格を理解しておくことで、過剰に高額なサービスはもちろん、安すぎる費用にも飛びつかずに本質を見極めることが重要です。市場の平均よりも安すぎる場合は、コストを下げられる何らかの理由があるはずです。提供されるサービス内容と期待できる成果のバランスを、自社の目的と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。
もう一つ、運用代行サービスを利用する上で課題となりやすいのが、ブランド理解の深度です。企業の理念や商品・サービスに込められた想い、細かなニュアンスまでを100%外部の人間が汲み取るのは容易ではありません。この認識のズレが、意図しないトーンの投稿や、ユーザーコミュニケーションの齟齬に繋がる可能性も否定できません。これを防ぐには、契約前に自社の状況を徹底してヒアリングしてくれるか、そして運用開始後に密なコミュニケーションを取れる体制があるかを確認することが不可欠です。
そして、「全てお任せ」の丸投げ状態は、社内にSNS運用のノウハウが蓄積されにくいというデメリットも生みます。将来的に内製化を目指すのであれば、SNS運用代行サービスを「パートナー」と捉え、積極的に関与し、学ぶ姿勢が重要になります。
| 項目 | 利点 | リスク・注意点 |
|---|---|---|
| 専門性・ノウハウ | 最新トレンド・アルゴリズムへの対応、データに基づいた戦略的な運用が可能 | 業者によりスキルや実績に差がある |
| リソース | 社員はコア業務に集中可能、運用工数の削減 | 外部委託コストが発生 |
| 戦略性・客観性 | 客観的視点からの分析・改善提案 | ブランド理解や企業文化の共有が不十分だと、戦略とのズレが生じる可能性 |
| コンテンツ品質 | プロによる質の高いクリエイティブ制作(画像、動画など) | 企業の意図と異なるテイストのコンテンツが制作されるリスク |
| コスト | 人材採用・育成コストと比較した場合の効率化 | 費用対効果の見極めが重要、「安かろう悪かろう」に注意 |
| ブランド理解 | 多様な業界知見を活かした提案 | 企業理念や細かなニュアンスの伝達不足によるミスマッチのリスク |
| 社内ノウハウ | 連携を通じて最新の知見に触れられる | 「丸投げ」状態だと社内にノウハウが蓄積されにくい |
| 業者選定 | 多数の選択肢から自社に合う専門家を選べる | 信頼できるパートナーを見極める目が必要、選定に時間と手間がかかる場合がある |
「SNS運用代行サービスに依頼すれば、すぐに成果が出る」というのも、よくある誤解の一つです。特にブランド認知の向上やファンの育成には、ある程度の時間と辛抱強い継続が必要です。例えば、立ち上げたばかりのアカウントに一瞬でフォロワーが数万人つくような即効性を期待するのではなく、長期的な視点で共にブランドを育ててくれるパートナーを見つけることが、SNS運用代行サービス活用の鍵と言えるでしょう。
ハイブリッド運用とは?最適な役割分担で相乗効果を狙う
ここまで、自社運用とSNS運用代行サービス活用のメリットとデメリットを見てきました。では、両者の「いいとこ取り」はできないのでしょうか?それを実現するのが「ハイブリッド運用」という考え方です。これは、社内チームと外部の専門家(SNS運用代行サービス)が、それぞれの強みを活かせるように業務を分担し、協力してSNSアカウントを運用していく体制を指します。
役割分担の最適な形は、企業の状況や目的によって様々です。「戦略立案や効果測定・分析といった専門知識が求められる部分はSNS運用代行サービスに依頼し、日々の投稿アイデア出しの一部や、顧客とのタイムリーなコメント対応は自社で行う」といった形が考えられます。あるいは、「コンテンツの企画や骨子は自社で固め、魅力的な画像や動画制作といったクリエイティブ面をプロに任せる」という分担も有効でしょう。
このハイブリッド運用がもたらす最大のメリットは、相乗効果です。SNS運用代行サービスの専門知識や客観的な視点を取り入れつつ、自社ならではのブランドへの深い理解や顧客との距離の近さを運用に反映できます。また、全ての業務を内製化するよりも、あるいは全てを外部に委託するよりも、必要な部分だけをプロに任せることで、コスト効率を高められる可能性があります。
そして何より重要なのは、SNS運用代行サービスとの連携を通じて、社内担当者が専門知識や運用スキルを実践的に学び、徐々にノウハウを蓄積していける点です。これは、将来的な内製化へのステップともなり得ますし、企業全体のSNS対応力を底上げすることにも繋がります。
ハイブリッド運用の具体的な分担パターンとしては、以下のようなものが考えられます。
戦略・分析支援型:企業が日々の投稿や顧客対応を担当し、SNS運用代行サービスが全体の戦略設計、高度なデータ分析、月次の改善提案、最新トレンドの共有など、専門的なコンサルティングで支援する。
コンテンツ制作支援型:企業が企画の方向性や伝えたいメッセージを明確にし、SNS運用代行サービスがそれを基に高品質な投稿コンテンツ(画像、動画、コピーライティング)を制作する。企業の「想い」とプロの「表現力」を融合させるパターンです。
部分業務委託型:日常的なコメント監視や定型的な問い合わせ対応、キャンペーン事務局業務など、特定の運用業務をSNS運用代行サービスに委託し、社内リソースをより戦略的な業務に集中させる。
実際に、私たちの支援現場でも、クライアント企業様と密に連携を取りながら、戦略策定からコンテンツ制作、効果検証までを二人三脚で進めることで、大きな成果に繋がった事例が多数あります。例えば、ある飲食店様では、私たちがLINE運用の戦略提案や配信コンテンツの作成を行い、店舗様側にはお客様の反応や現場の声をフィードバックしていただくことで、顧客満足度の向上とリピーター獲得に成功しました。
ハイブリッド運用成功のポイントと導入ステップ
ハイブリッド運用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントと、導入に向けた具体的なステップがあります。
ハイブリッド運用成功のポイント
- 明確な目標設定とその共有:まず、SNS運用を通じて何を達成したいのか(KGI)、そのために何を指標とするのか(KPI)を具体的に設定し、社内チームとSNS運用代行サービスの間で完全に共有することが不可欠です。目標が曖昧では、適切な役割分担も効果測定もできません。
- 役割と責任範囲の明確化:「どこからどこまでを自社が担当し、どこからをSNS運用代行サービスに任せるのか」「最終的な意思決定は誰が行うのか」といった役割分担と責任範囲を、事前に明確に定めておくことが混乱を防ぎます。
- 信頼できるパートナーの選定:SNS運用代行サービスを選ぶ際は、実績や専門性はもちろんのこと、自社の業界や課題に対する理解度、提案内容の具体性、そして何よりも「自社との相性」を重視しましょう。
- 徹底したコミュニケーションと信頼関係:定期的なミーティングの実施、迅速な情報共有、建設的なフィードバックの交換ができる体制を構築しましょう。特に、SNS運用代行サービスの担当者との相性や、コミュニケーションのしやすさは非常に重要です。信頼できるパートナーシップが、ハイブリッド運用の土台となります。
- 社内体制の整備と協力:投稿内容の承認フローの迅速化、社内関連部署との情報共有の円滑化など、社内側の協力体制も成果を大きく左右します。「SNS運用代行サービスに任せたから、あとは何もしなくていい」という姿勢では、期待する成果は得られにくいものです。
- 長期的な視点と柔軟性:SNS運用は、すぐに結果が出るものではありません。特にブランド構築やファンの育成には時間がかかります。焦らず長期的な視点を持ち、状況の変化に応じて運用方針や役割分担を柔軟に見直していく姿勢が大切です。時には、「あえてバズを狙わない」選択や、「フォロワー数よりもエンゲージメントの質を重視する」といった、本質的な価値を見据えた判断も必要になります。
ハイブリッド運用導入の具体的なステップ
- 現状分析と課題の明確化:まず、自社のSNS運用の現状(目的、ターゲット、運用体制、リソース、スキル、成果、課題など)を客観的に把握します。
- SNS運用の目的と目標(KGI・KPI)設定:ハイブリッド運用を通じて何を達成したいのか、具体的な数値目標を設定します。
- 業務の洗い出しと役割分担の検討:SNS運用に関わる全ての業務(戦略立案、コンテンツ企画、素材収集、撮影、ライティング、デザイン、投稿作業、コメント対応、広告運用、効果測定、レポーティングなど)をリストアップし、自社で担う部分とSNS運用代行サービスに委託したい部分を具体的に検討します。
- パートナーとなるSNS運用代行サービスの選定:複数のSNS運用代行サービスから情報収集し、提案を受け、実績、専門性、費用、そして何よりも自社との相性を考慮してパートナーを選定します。なお社内の知見によっては、先に信頼できるパートナーを選定し、相談しながら具体的な役割分担を決めていく方法も有効です。
- 契約締結と運用体制の構築:契約内容(サービス範囲、費用、期間など)、役割分担、コミュニケーションルール、情報共有の方法、承認フローなどを明確に取り決め、具体的な運用体制を構築します。
- 運用開始と定期的な効果測定・改善:計画に沿って運用を開始し、定期的に効果測定を行います。その結果を基に、社内チームとSNS運用代行サービスが協力して課題を分析し、改善策を実行していくPDCAサイクルを回します。
ハイブリッド運用は、導入して終わりではありません。市場やSNSプラットフォームのトレンドは常に変化します。そのため、定期的に運用体制や戦略を見直し、最適化していくことが、長期的な成功に繋がります。
まとめ:今こそ「いいとこ取り」のSNS運用へ
本記事では、SNS運用における「自社運用」「SNS運用代行サービスの活用」、そして両者の強みを融合させた「ハイブリッド運用」について解説してきました。
自社運用はブランドへの深い理解を活かせますが、専門知識やリソースの確保が課題となることがあります。一方、SNS運用代行サービスは専門的な知見で運用をサポートしてくれますが、コストやブランド理解の共有といった点に注意が必要です。
そして、ハイブリッド運用は、これらのメリットを最大限に引き出し、デメリットを補い合う、まさに「いいとこ取り」の戦略と言えるでしょう。現代の複雑で変化の速いSNS環境において、多くの企業にとって非常に合理的かつ効果的な選択肢となり得ます。
大切なのは、「SNS運用を通じて何を達成したいのか」という目的を見失わず、自社の状況やリソース、そして目指すべきゴールに合わせて、最適な運用の形を模索し続けることです。その過程で、SNS運用代行サービスは、戦略立案から実行、効果測定、そして社内ノウハウの育成に至るまで、心強いパートナーとなり得るでしょう。
この記事が、皆様のSNS運用戦略の一助となれば幸いです。まずは、自社のSNS運用の現状を見つめ直し、ハイブリッド運用という新たな可能性を検討してみてはいかがでしょうか。
SNS運用代行ならクロス・プロップワークス
クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!