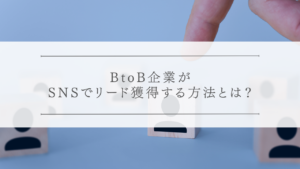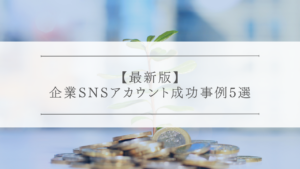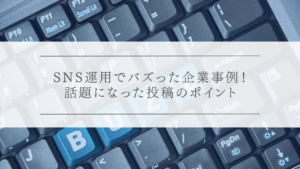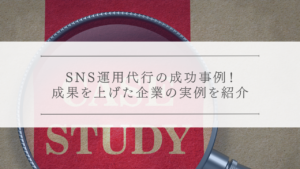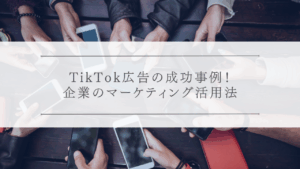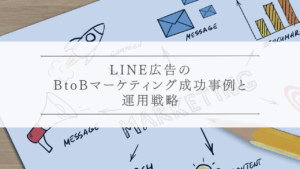SNSはBtoCビジネスにおいて、ユーザーとの距離を縮め、購買行動に直結させるための強力なツールです。しかし、実際にどのようにSNSを活用すれば成果が出るのか、悩んでいる担当者も多いのではないでしょうか。私たちの調査でも、消費者の約3割がSNSをきっかけに商品を購入した経験があると回答しており、その重要性は増すばかりです。この記事では、BtoC企業がSNSで成功を収めた5つの事例を取り上げ、その華やかな成果の裏側にある、泥臭くも本質的な戦略と思考法を、私たちプロの視点から深く掘り下げて解説します。
SNSマーケティングがBtoC企業にもたらす本当の影響とは?
SNSは、もはや単なる「情報発信ツール」ではありません。消費者が商品やサービスと出会い、評価し、関係を築くまでのプロセス全体を根本から変える存在となっています。
その一つが、情報収集の手段としての変化です。私たちの調査によると、10代や20代の若年層は、何かを調べるときにGoogleだけでなく、InstagramやX(旧Twitter)を検索エンジンとして活用しています。これは、単なる行動の変化ではありません。ユーザーはキーワードで答えを探す「解決策の探索」から、ハッシュタグなどを通じて理想のライフスタイルや雰囲気を探す「インスピレーションの探索」へと移行しているのです。例えば、「#夏コーデ」で検索するユーザーは、服そのものだけでなく、それがもたらす気分や体験を求めています。この違いを理解することが、現代のSNSコンテンツ戦略の第一歩と言えるでしょう。
さらに、SNSは発見から購買までの道のりを劇的に短縮しました。Instagramでは32.8%、TikTokでは29.1%のユーザーが、プラットフォーム上での情報がきっかけで購入経験があると回答しています。これは、魅力的なショート動画や投稿一つで、ユーザーを数分後には購入完了まで導ける可能性があることを示しています。つまり、企業アカウントは「デジタルの店舗」そのものであり、プロフィールや商品タグ、ショッピング機能は、今や必須のインフラなのです。
ただし、すべてのSNSが同じ役割を担うわけではありません。例えば、LINEをきっかけとした直接の購入経験率は14.5%と他のSNSに比べて低い一方で、クーポン配信やチャットなど、一度関係を築いた顧客とのコミュニケーションには絶大な効果を発揮します。Instagramで新規顧客を獲得し、商品に同梱したQRコードからLINEの友だちになってもらい、そこで信頼関係を深めてリピート購入につなげる。このように、各プラットフォームの特性を理解し、顧客の体験を途切れさせない戦略を描くことが、専門的なSNS運用代行サービスが提供する価値の核心でもあります。
成功事例①:無印良品-“世界観”でファンを育てるInstagram運用
無印良品のInstagram成功の本質は、ミニマルでおしゃれな写真を投稿することだけではありません。ブランドの価値をユーザー自身に定義してもらう仕組みを巧みに作り上げ、顧客をブランドストーリーの参加者に変えている点にあります。
彼らのフィードは、商品単体ではなく、実際の生活空間に商品が溶け込んでいる様子を中心に投稿されています。これにより、ユーザーは商品の利用シーンを具体的にイメージできます。
特に象徴的なのがハッシュタグを活用したUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用です。企業が「こう使ってください」と一方的に提示するのではなく、「皆さんはどう使っていますか?」と問いかけ、集まった素晴らしいアイデアを公式アカウントで紹介する。これは、ユーザーからの推薦という、広告よりもはるかに信頼性の高い情報をブランドの資産に変える見事な戦略です。さらに、ファンやインフルエンサーと共に商品を開発する「共創プロジェクト」も行っており、コミュニティの声を真摯に聞く姿勢を示しています。
多くの企業が「どう見せるか」に腐心する中、無印良品は「どう使ってもらうか」をユーザーに委ね、その集合知をブランドの資産に変えています。これは、一方的な情報発信から雙方向の価値共創へとシフトする、現代SNSマーケティングの理想形の一つです。
成功事例②:鳥羽水族館-“動物たちの個性”で魅せるTikTok活用術
鳥羽水族館のTikTokは、動物を単なる「展示物」としてではなく、それぞれが個性を持った「キャラクター」として描くことで、多くのファンを魅了しています。
特に人気なのが、ラッコの「メイ」と「キラ」です。投稿では、2頭の個性的な仕草や関係性が伝わるようなストーリー性のある動画が数多く見られます。もちろん、流行の音楽に合わせた短い動画というTikTokの基本もしっかりと押さえています。
特筆すべきは、イベントの活用です。「ラッコ飼育40周年記念」のような特別なイベントでは、TikTokでライブ配信を実施し、そのアーカイブをYouTubeに公開することで、プラットフォームを横断したコンテンツ展開を行っています。このライブ配信のアーカイブは7.5万回以上再生されるなど、高いエンゲージメントを獲得しました。
動物に名前を付け、その個性を伝えることで、単なる「可愛い動物の動画」は「続きが見たくなる物語」へと昇華します。コメント欄には「メイちゃん」「キラちゃん」と、まるで友人のように名前を呼ぶファンの声が溢れており、これが深い感情的なつながりを生んでいる証拠です。鳥羽水族館の成功は、コンテンツを「記録」ではなく「物語」として捉えている点にあります。ユーザーはラッコを見に来るのではなく、「メイちゃん」に会いに来るのです。このキャラクター化戦略こそが、一過性のバズで終わらない、持続的なエンゲージメントを生む秘訣です。
成功事例③:岡山市-“尖った企画”でバズを生むYouTube戦略
厳密には企業ではありませんが、その手法がBtoCマーケティングとして非常に参考になる「自治体」の事例を紹介します。岡山市のYouTube戦略は、ブランドが持つ従来の堅いイメージを打ち破り、プラットフォームの文化に寄り添うことで大きな成果を上げた好例です。
岡山市は、市のPR動画にお笑いコンビ「空気階段」を起用しました。重要なのは、彼らに紋切り型のPRをさせるのではなく、芸人としての面白さを最大限に活かしたエンターテイメント性の高いコンテンツを制作した点です。その結果、動画は大きな話題を呼び、多くのメディアに取り上げられました。
多くの企業や自治体のYouTubeチャンネルが失敗する理由は、YouTubeを単なるテレビCMや公式発表の置き場所として扱ってしまうからです。岡山市は、YouTubeで成功するためには、動画をアップロードするだけでなく、視聴者が面白いと感じる「YouTubeの動画」を作らなければならないことを理解していました。
この事例の最大の教訓は、「郷に入っては郷に従え」ということです。岡山市は、YouTubeというプラットフォームの文脈を理解し、自治体としての「かくあるべき」という姿を一度横に置きました。その結果、広告らしくない、純粋に面白いコンテンツが生まれ、多くの共感を呼びました。ブランドの品位を保ちつつ、プラットフォームの文化に寄り添う勇気が、時として最大の成果を生むのです。
成功事例④:パインアメ-“遊び心”で企業間も巻き込むX(旧Twitter)
パインアメのX(旧Twitter)公式アカウントは、一貫した親しみやすいブランド人格を確立し、プラットフォームの文化に積極的に参加することで、一つのキャンディをオンライン上の愛される存在へと変えました。
彼らの投稿は、「は」をカタカナの「パ」で表記したり、飴の形を模した「🍍」という絵文字を使ったりと、非常にユニークで一貫したトーンを持っています。2月22日の「猫の日」には、商品である「パインアメ」を猫の形に見立てた「パインニャメ」という画像を投稿し、その遊び心と時事性で大きな反響を呼びました。
さらに、他の企業アカウントとも頻繁に交流し、まるでブランド同士が友達であるかのような、見ていて楽しいコミュニケーションを繰り広げています。これは、自社アカウントのファンだけでなく、交流相手のアカウントのファンにも認知を広げる、非常に巧みな戦略です。
パインアメのアカウントは、製品を売るのではなく、「ブランドの人格」を伝えています。この「人格」にファンがつくことで、結果的に製品への愛着が深まるのです。企業アカウントが成功するためには、単なる情報発信者ではなく、プラットフォーム上の魅力的な「一人のユーザー」として振る舞うことが、時に最も効果的な戦略となります。
成功事例⑤:のらぎや-“寄り添う姿勢”で信頼を築くLINE活用
こちらは、私たちがご支援しているクライアント様の事例です。ECサイトを運営する「のらぎや」様は、LINEを活用してニッチな市場で顧客との深い信頼関係を築いています。
「のらぎや」様の主なターゲットは「農業女子」という非常に専門的な層です。そこで私たちは、LINEを単なるセールス情報の告知ツールとして使うのではなく、ターゲットが抱える悩みに寄り添うコラムなどを配信し、ブランドを「頼れる味方」として位置づける戦略を取りました。もちろん、「友だち追加で300円OFFクーポン」の提供や、商品発送時にQRコードを同梱するなど、友だち登録を促し、メリットを感じてもらうための基本的な施策も徹底しています。
私たちが「のらぎや」様をご支援する中で最も重視したのは、LINEを単なる販促ツールではなく、お客様との「信頼関係を育む場」と位置づけることでした。ECという顔の見えないビジネスだからこそ、有益な情報提供を通じてお客様に寄り添う姿勢を見せることが、結果的にブロック率を下げ、エンゲージメントを高める鍵となります。これは、多くの企業が見落としがちな、LINE運用の本質的な価値です。
成功事例から学ぶ、SNS運用代行サービスが実践する共通の思考法
これらの多様な成功事例は、決して偶然の産物ではありません。そこには、プロフェッショナルな運用を支える共通の思考法が存在します。これこそが、専門的なSNS運用代行サービスが提供する本質的な価値です。
①明確なターゲット設定:ペルソナは「実在する一人」まで深掘りする
多くの企業が「30代女性」といった大まかなターゲット設定に留まりがちです。しかし、プロの現場では、ターゲットを「実在する一人」の人物像、すなわちペルソナとして具体的に描き出します。例えば、「不動美梨さん、50歳、スナック経営」という情報だけでは不十分です。「彼女は新しい日本酒を探している」「好奇心旺盛な性格」といった内面まで深く理解することで、初めて心に響くコンテンツが生まれます。彼女が求めているのは有名な銘柄ではなく、「利き酒師の店長があなたがであったことのない日本酒をお届け」といった、まだ見ぬ発見を予感させる情報なのです。
②コンテンツの一貫性:「バズ」より「じわじわ効く信頼」を築く
短期的なバズを追いかけるあまり、ブランドイメージが一貫しなくなるのはよくある失敗です。今回紹介した成功事例はすべて、一貫した世界観やトーンを保っています。無印良品の静かな佇まい、パインアメの陽気な遊び心。ユーザーは、そのアカウントに触れることで得られる体験を予測できるため、安心してフォローし続けます。一過性のバズは短期的なトラフィック増に過ぎませんが、築き上げた信頼は長期的なブランド資産となります。プロのSNS運用代行サービスは、この長期的な信頼の構築を最も重要な責務と捉えています。
③分析と改善のサイクル:成果を出すアカウントの「心臓部」
「投稿して、あとは祈るだけ」では、アカウントは成長しません。私たちの調査では、SNS運用が成功している企業とそうでない企業を分ける最大の要因は、「データ分析に基づいた改善サイクル(PDCA)を回せているか」という点でした。
これは具体的にどういうことか、実際のレポート例で見てみましょう。
| 配信コンテンツ | ターゲット | 開封率 | クリック率 | 分析と次のアクション |
|---|---|---|---|---|
| 煎茶ワークショップ&無添加マルシェ | 30代 | 55.2% | 3.8%(マルシェに集中) | 30代は「食」への関心が高い。次回はマルシェ企画をメインに訴求。 |
| 煎茶ワークショップ&無添加マルシェ | 40代 | 55.8% | 8.2%(煎茶ワークショップに集中) | 40代は「学び・文化」への関心が高い。次回は文化体験型イベントを訴求。 |
この表が示すように、同じ内容の配信でも、ターゲットによって反応は全く異なります。30代は「マルシェ」に、40代は「煎茶ワークショップ」に強く反応しました。このデータに基づき、次回の配信内容をそれぞれのターゲットに合わせて最適化する。この地道な分析と改善の繰り返しこそが、成果を出すアカウントの心臓部であり、専門的なSNS運用代行サービスが日々実践しているプロセスなのです。
まとめ:SNS成功の裏側にある、3つの共通思考法
SNSでの成功は、運や偶然によってもたらされるものではありません。それは、 ①ユーザーを深く理解し(ペルソナ設定)、②長期的な視点でブランドを育み(信頼の構築)、③データに基づいて絶えず改善を続ける(PDCAサイクル) という、規律に基づいた活動の賜物です。
これらの戦略を自社だけで実行するには、専門的な知識と多くのリソースが必要となります。BtoCビジネスの成長を加速させるため、専門家の知見を活用したいと考える企業にとって、SNS運用代行サービスは非常に有効な選択肢となるでしょう。本記事で紹介した思考法が、皆様のSNS運用のヒントになれば幸いです。
SNS運用代行ならクロス・プロップワークス
クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!