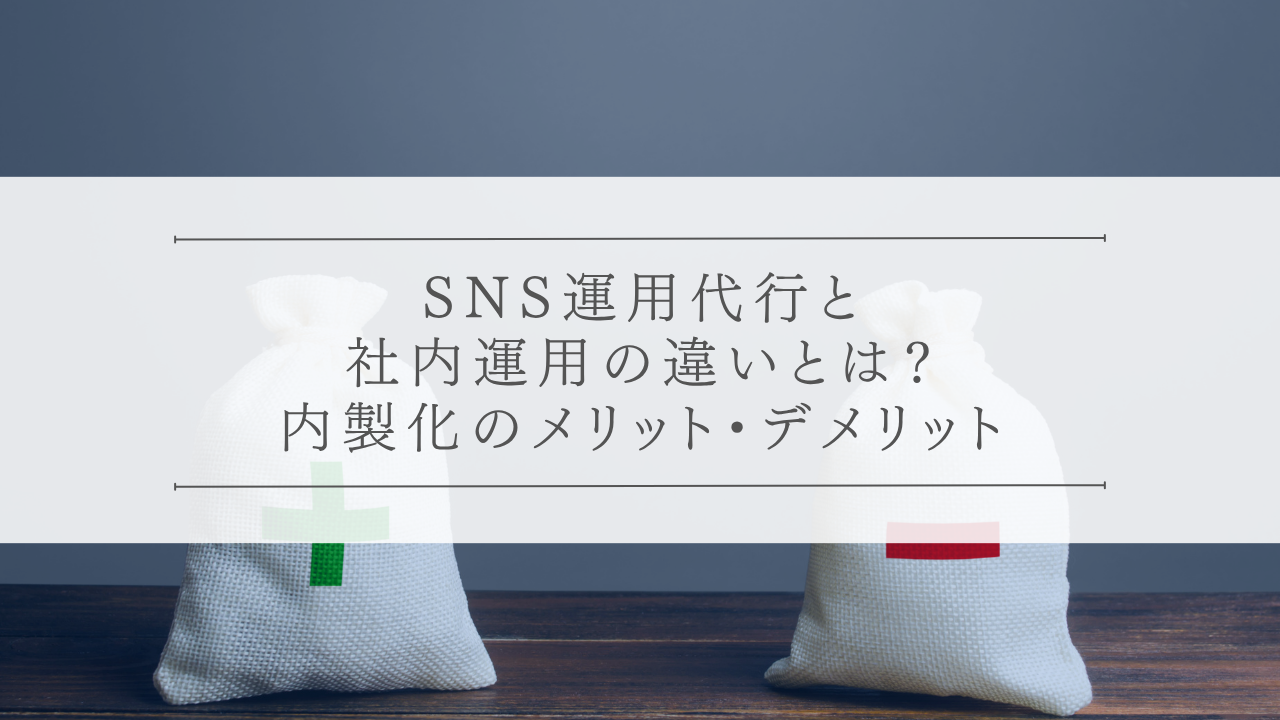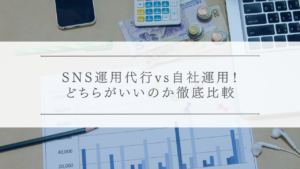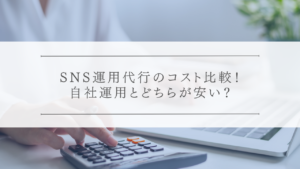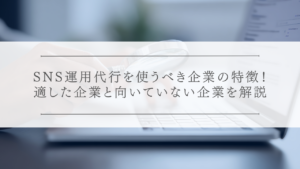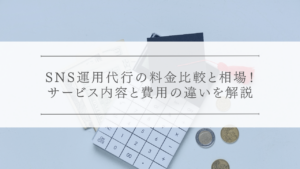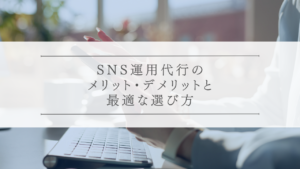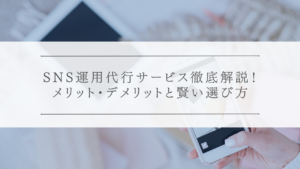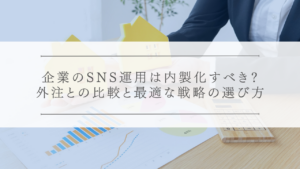企業活動においてSNSは不可欠なマーケティング手段です。その運用には「SNS運用代行」と「社内運用(内製化)」の2択がありますが、この選択は単にメリット・デメリットを比較するだけでは不十分です。成功の鍵は、コスト、専門性、スピード感といった様々な側面における両者の本質的な違いを深く理解することにあります。本記事では、その”違い”に焦点を当て、貴社が最適な選択をするためのポイントをプロの視点から解説します。
SNS運用代行とは?依頼できる内容と特徴
SNS運用代行サービスは、専門企業がSNSアカウント運用を代行するサービスです。業務範囲は戦略立案から投稿作成、コメント対応、効果測定、広告運用まで多岐にわたります。
主な業務には、目的やターゲットを設定する戦略設計、魅力的なコンテンツ企画・制作、定期的な投稿代行・運用管理、成果を分析し改善提案を行う効果測定・レポーティング、そして必要に応じたSNS広告運用が含まれます。
企業がSNS運用代行を導入する背景には、自社内における専門知識やリソースの不足、コンテンツ企画の難しさがあります。特にInstagramは、写真や動画といったビジュアルコンテンツの質、統一された世界観の構築、アルゴリズムに最適化されたハッシュタグ戦略など、他のSNSと比較して求められる専門性が高いため、外部委託が多い傾向です。
よくある誤解は「任せればすぐに成果が出る」という期待ですが、SNS運用は戦略と継続的な改善が不可欠で、成果には時間が必要です。この「成果が出るまでのタイムラグ」への認識のズレが、後の不満やトラブルに繋がる最大の原因の一つであり、契約前に現実的な成果目標と期間のすり合わせが極めて重要です。
社内運用(内製化)の特徴と取り組み方法
社内運用(内製化)とは、自社従業員がSNS運用業務全般を主体的に行うことです。
具体的な社内体制は、1人の担当者が全ての業務を担う専任担当者、通常業務と並行して運用を行う他業務との兼任、マーケティング部や広報部、商品開発部など複数部署のメンバーが集まる関連部門のチーム運用など様々です。重要なのは、意思決定権者や緊急時の報告体制といったガバナンスの確立です。例えば、「投稿内容の承認フローと責任者」「コメントやDMへの返信ルールと担当範囲」「個人情報や機密情報の取り扱い規定」「炎上発生時の具体的な報告ルートと初期対応手順」などを事前に明確化しておく必要があります。しかし、多くは兼任でリソース配分が課題となりがちです。
一般的な運用フローは、①目的設定とターゲット明確化、②運用計画とコンテンツカレンダー作成、③コンテンツ企画・制作、④投稿とユーザーコミュニケーション、そして⑥効果測定・分析と改善のPDCAサイクルです。しかし、特に兼務担当者の場合、日々の業務に追われ、このPDCAサイクルの「C(効果測定・分析)」や「A(改善策)」の部分が疎かになりがちで、結果として運用がマンネリ化したり、成果に繋がらないといった課題が生じやすいのが実情です。
SNS運用代行のメリット・デメリット
SNS運用代行サービスの利用にはメリットとデメリットがあります。
SNS運用代行のメリット
- 専門知識・ノウハウの活用:SNS運用のプロの知見を活用し、最新トレンドに対応した運用が期待できます。
- リソースの最適化・社内負担の軽減:企画から分析まで委託し、社員はコア業務に集中できます。
- 客観的な分析と戦略的な運用:第三者の視点で客観的なデータ分析に基づいた改善提案を受けられます。
- 高品質なコンテンツ制作:専門のクリエイターが高品質なコンテンツを制作します。
- 安定した運用体制の確保:社内担当者の変動リスクを避け、継続的な運用が可能です。
SNS運用代行のデメリット
- コストの発生:外部委託のため費用が発生します。月額数十万円以上かかることもあります。
- コミュニケーションコストと認識の齟齬:情報共有が不十分だと、企業の意図が伝わらない可能性があります。
- 情報漏洩のリスク:内部情報を共有するため、委託先のセキュリティ体制の確認が必要です。
- 社内にノウハウが蓄積しにくい:「丸投げ」状態だと知見が蓄積されにくいですが、例えば、定期的なレポーティングの際に詳細な分析内容や施策の意図を共有してもらう、社内担当者も運用ミーティングに積極的に参加し質疑応答を行う、部分的にでも社内担当者が運用に関わるといった体制を取ることで、ノウハウの吸収を促すことは可能です。
- 「自社の声が届きにくくなる」という誤解と、その逆の可能性:優れたSNS運用代行サービスは、深いブランド理解を通じて「自社では気づかなかった魅力」を発信してくれることがあります。重要なのは業者を「戦略パートナー」と捉えることです。
社内運用(内製化)のメリット・デメリット
社内運用(内製化)にも、SNS運用代行とは異なる利点と課題があります。
社内運用(内製化)のメリット
- 深いブランド・商品理解と「生の声」の発信:自社スタッフが運用することで、熱意ある「生の声」を発信しやすくなります。
- 迅速な情報発信と意思決定:社内でプロセスが完結するため、情報伝達や意思決定が速く、柔軟に対応できます。
- コスト抑制:外部委託費はかかりませんが、人件費や機会損失といった「見えないコスト」を考慮する必要があります。
- 社内へのノウハウ蓄積:日々の運用を通じて得られた知見やスキルが企業の資産として蓄積されます。
- 顧客との直接的で密な関係構築:社員が直接対応することで、顧客との信頼関係を深めやすくなります。
社内運用(内製化)のデメリット
- リソース不足(人材・時間・スキル):専門スキルと時間が必要ですが、兼任担当者が多く、運用が中途半端になるリスクがあります。
- 専門知識・最新ノウハウの不足:SNSのトレンドやアルゴリズムは常に進化しており、自己流の運用では効果が出にくいことがあります。例えば、ターゲット層とズレたプラットフォームを選んでしまう、既に時代遅れとなったテクニックを使い続ける、著作権や肖像権への配慮が不十分なコンテンツを投稿してしまう、といった失敗が起こりやすくなります。
- コンテンツの質のばらつき・属人化:投稿の質が担当者に左右されやすく、異動や退職で運用ノウハウが失われるリスクがあります。
- 客観性の欠如と「ひとりよがり」な発信:社内視点に偏り、ユーザーが求める情報とズレた発信になる可能性があります。
- 炎上リスクへの対応体制の不備:不適切な投稿による炎上リスクに対し、社内体制が不十分だと企業イメージを損なう恐れがあります。一度失ったブランドの信頼を回復するには、多大な時間とコスト、そして労力が必要となることを肝に銘じておくべきです。
- SNS運用における「成果」への誤解:SNS運用は短期で大きな成果が出るものではなく、ブランドへの信頼を時間をかけて築く長期的な取り組みです。短期的な指標に一喜一憂せず、中長期的な視点での成果を見据えることが重要です。
どちらを選ぶべき?SNS運用代行と社内運用の判断基準とおすすめの体制
SNS運用代行と社内運用、どちらが最適かは企業の状況や目的で異なります。
SNS運用代行と社内運用のメリット・デメリット比較一覧
| 特徴(Feature) | SNS運用代行(SNSOperationOutsourcing) | 社内運用(内製化) (In-houseOperation) |
|---|---|---|
| メリット(Merits) | 専門知識・ノウハウ活用リソース最適化・負担軽減客観的分析・戦略的運用高品質コンテンツ安定した運用体制 | 深いブランド理解・生の声迅速な情報発信・意思決定コスト抑制(表面的)社内ノウハウ蓄積顧客との直接的関係構築 |
| デメリット(Demerits) | コスト発生コミュニケーションコスト情報漏洩リスク社内ノウハウ蓄積しにくい | リソース不足専門知識不足質のばらつき・属人化客観性の欠如炎上リスク対応の課題 |
SNS運用代行と社内運用の選定の判断基準
- 企業の目的とSNS運用の位置づけ:売上やリード獲得が主目的か、ブランド認知やエンゲージメント強化が主目的か。
- 社内リソース(人材・スキル・予算):運用に割ける人的リソース、専門スキルを持つ人材の有無、予算規模。
- 求める成果とスピード:短期間での成果を求めるか、長期的なブランド育成を目指すか。一般的に、専門知識とリソースを集中投下できるSNS運用代行サービスは短期間での成果創出に繋がりやすく、自社でじっくりとファンを育てていく社内運用は長期的なブランド育成に向いています。
- 対象とするSNSプラットフォームの特性:ビジュアルの質や世界観の統一が特に重要なInstagramなど専門性が高いプラットフォームはSNS運用代行が有効な場合があります。
- 企業の「本気度」と「継続する覚悟」:SNS運用を短期的な成果創出の手段と捉えるか、長期的な資産(ノウハウ・文化)形成と捉えるか。専門家の力で早期に成功事例を作りたい場合はSNS運用代行サービスが、時間をかけてでも自社の文化として根付かせたい場合は社内運用が適しています。SNS運用は片手間では成功しないため、企業としてどちらの方針でコミットしていくかを明確にすることが重要です。
おすすめの体制
- SNS運用代行サービスが適しているケース:社内に専門知識やリソースがない場合、複数SNSを横断的に活用したい場合、客観的データ分析に基づいた戦略的改善をしたい場合、SNSを起点とした包括的なデジタルマーケティング戦略を展開したい場合。
- 社内運用(内製化)が適しているケース:ブランドの世界観を自社で完全にコントロールしたい場合、顧客とのダイレクトなコミュニケーションを最優先したい場合、長期的に社内にノウハウを蓄積したい場合、予算が非常に限られている場合(ただし成果には時間と労力が必要)。
- ハイブリッド運用という選択肢:戦略立案や分析はSNS運用代行、日常的な投稿やコメント対応は社内、といった分担も可能です。また、企業の成長フェーズに応じて、委託範囲を柔軟に見直していくアプローチも有効です。例えば、事業立ち上げ初期は専門家の知見を最大限に活用し、事業が軌道に乗ってきたら徐々に内製化を進め、最終的には自立した運用体制を目指す、といった段階的な移行も検討できます。
まとめ:成功の鍵は、メリットの先にある本質的な違いの理解
SNS運用代行か内製化か、最適な選択は自社の目的とリソース次第です。本記事が、皆様のSNS戦略検討の一助となれば幸いです。最適な運用体制の選択は、時に難しい決断となります。もし迷われた場合は、複数のSNS運用代行サービス会社に現状の課題や目的を相談し、具体的な提案や見積もりを比較検討してみることから始めてみてはいかがでしょうか。そのプロセス自体が、自社にとって何が最適かを見極める貴重な機会となるはずです。
SNS運用代行ならクロス・プロップワークス
クロス・プロップワークスでは、「SNS運用代行・コンサルティングサービス」を提供しております。プライム市場上場のクロス・マーケティンググループの一員だからこそできる、マーケティング業務のプロ集団が、貴社のSNS運用をリードさせて頂きます。
運用目的に応じて採用方針を決定
SNS運用の目的を明確にした上で、運用方針や投稿内容の方向性を決定します。
・SNS運用の目的に沿ったkpiの設定
・ターゲット、ペルソナの設定
方針に沿った運用代行
運用方針に沿った投稿記事の作成から投稿、ユーザー対応などの日々の運用業務を代行します。
レポートをもとに内容を改善
月次レポートをもとに次回の投稿内容の改善を行います。
・月次オンラインMTGの実施
・アカウント活性化施策
気になることがあれば、どんなことでもお気軽にご相談ください!